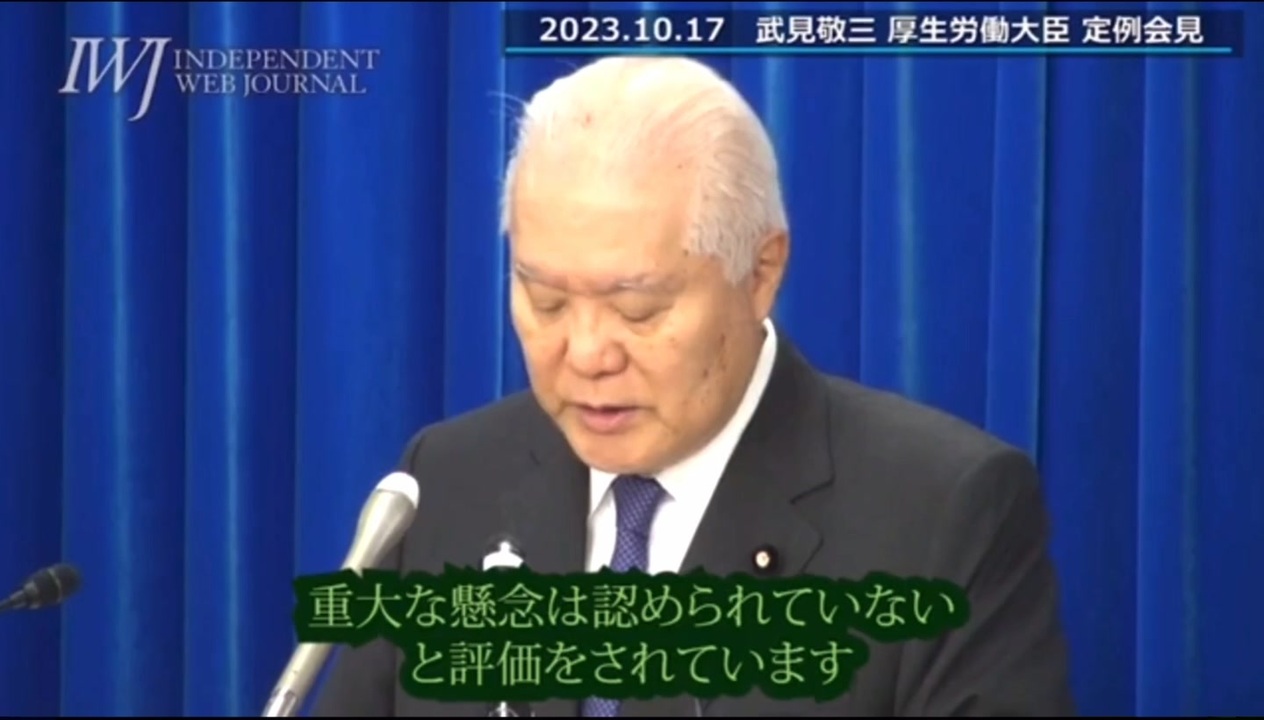武見 敬三(たけみ けいぞう、1951年〈昭和26年〉11月5日 - )は、日本の政治家、ニュースキャスター、国際政治学者。自由民主党所属の参議院議員(5期)、同党参議院議員会長(第31代)、元世界保健機関親善大使、そして元国連開発計画(UNDP)人間の安全保障に関する特別報告書ハイレベル諮問パネル共同議長。
厚生労働大臣(第27代)、厚生労働副大臣(第1次安倍内閣)、参議院外交防衛委員長、参議院環境委員長、自由民主党参議院政策審議会長を歴任した。元日蓮宗全国檀信徒協議会副会長(現在は顧問)。
来歴
松濤幼稚園、慶應義塾幼稚舎、慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校を経て、1974年(昭和49年)3月に慶應義塾大学法学部政治学科卒業、その後、同大学院法学研究科政治学専攻修士課程に入学、1976年修了。1980年(昭和55年)に同大学院法学研究科政治学専攻博士課程単位取得満期退学。
学生時代はラグビー部に属していた。東海大学政治経済学部助手、講師、助教授を経て、1995年(平成7年)に東海大学教授。専攻は国際政治学。米国の東アジア政策などについての論文が多い。途中台湾師範大学大学院・ハーバード大学大学院にて在外研究。
1987年(昭和62年)10月から1988年(昭和63年)10月までテレビ朝日「モーニングショー」のメイン司会者。1980年代には「CNNデイウォッチ」、1990年代には「CNNデイブレイク」のキャスター。1995年(平成7年)の第17回参議院議員通常選挙で初当選し、2001年に再選。日本医師連盟の推薦候補だが本人に医師免許はなく、知名度と政治学者としての専門を生かし、議員としても国際関係の討論番組などに盛んに出演していた。
2002年(平成14年)3月7日、喫煙による健康被害を防ぐため禁煙の必要性を主張する、超党派の国会議員で構成される禁煙推進議員連盟の設立発起人の一人となる。
2006年(平成18年)9月発足の安倍内閣で厚生労働副大臣(雇用対策や児童、家庭対策などの担当)。厚生労働副大臣でありながら、自身がメタボリックシンドロームになっていたことが判明し自身のリハビリ経験をホームページで公開した。
任期満了に伴い2007年(平成19年)7月29日に行われた第21回参議院議員通常選挙で三選を目指し比例代表区から立候補したが、自民党への逆風の煽りを受けて18万5千票を集めるものの35名中15位(当選者14名)で次点で落選する。
2007年(平成19年)11月、米国ハーバード大学医療財政研究所に客員研究員として就任。2008年(平成20年)、長崎大学客員教授。2012年(平成24年)、身延山大学客員教授に就任。同年11月30日、上位当選者の義家弘介が12月4日公示の第46回衆議院議員総選挙への立候補を理由に参議院議員を辞職し、繰り上げ当選で5年ぶりに国政復帰した。
2013年(平成25年)、第23回参議院議員通常選挙東京都選挙区の自民党公認候補に内定する。同年7月、第23回参議院議員通常選挙に東京都選挙区から立候補し、再選。
2017年(平成29年)、参議院自民党政策審議会長(衆議院側の政調会長に該当する)に就任、参議院の政策立案を牽引する。政審会長として包括的な政策の検証を行うとともに長期的な観点から日本の在り方の方向性を議論した「国家ビジョン」を内政と外交について取りまとめた。この内容は「参議院自民党『内政・外交国家ビジョンセミナー(JAPAN VISIONS)』」としてニコニコ動画でも特集された。
2019年(令和元年)、世界保健機関ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ親善大使に就任する。
2019年7月21日投開票の第25回参議院議員通常選挙に東京都選挙区から立候補し、6位(定数6)で当選。
2020年(令和2年)7月には新型コロナウイルス感染拡大と厚生労働省のガバナンス等について課題を提起し、新型コロナウイルス関連肺炎対策本部のもとに感染症対策ガバナンス小委員会を立ち上げた。そして、2020年10月に今回の反省点を踏まえ、感染症有事において、1.国レベルの安全保障における感染症危機の明確な位置づけ、2.感染症危機管理に特化した組織機構の構築等、3.医療、公衆衛生、危機対応オペレーション、研究開発の4機能の一体運用、4.感染症危機対応のIT化等、5.国民と政府の関係とコミュニケーションの強化、6.柔軟な制度運用を可能とする法的枠組みと手順の構築、7.産官学の連携による医薬品研究開発ファンドの設立、8.国立感染症研究所のワクチン業務の見直しを委員長として取りまとめた。
2021年(令和3年)、国連開発計画(UNDP)が設置の発表をした「人間の安全保障に関する特別報告書ハイレベル諮問パネル」の共同議長として、ラウラ・チンチージャ元コスタリカ大統領とともに就任した。そして、パネルでの議論を通じて、持続可能な開発目標(SDGs)達成を始めとする地球規模の課題への取組を加速するため、新たな時代の人間の安全保障について報告書を取りまとめた。
2022年(令和4年)1月には、自由民主党の中に、社会保障調査会とデジタル社会推進本部の合同のプロジェクトチーム(PT)として「健康・医療情報システム推進合同PT」を立ち上げ、事務局長に就任した。新型コロナ感染症に対する危機管理の経験も基に、①「全国医療情報プラットフォーム」の創設、②電子カルテ情報の標準化、③「診療報酬改定DX」の取組を並行して進めるよう求める「医療DX令和ビジョン2030」を5月に提言している。
2023年(令和5年)9月13日発足の第2次岸田第2次改造内閣で厚生労働大臣に就任し、初入閣。
同年10月1日、石破茂内閣の発足に伴い厚生労働大臣を退任。同月4日に参議院環境委員長に就任。同年11月6日、自民党参議院議員会長に就任。
同年12月26日、翌年7月の第27回参議院議員通常選挙の東京都選挙区公認候補として擁立することが自民党から発表された。
活動
海洋基本法の制定に尽力した他、自殺対策基本法、JICA改革など多くの議員立法・行政改革に携わった。その評価は国際的にも高く、様々な国際的専門家会議に招聘されており、2019年には保健問題に関する実質的な活動を担うことを期待されWHO(世界保健機関)の親善大使に就任した。国際的なトップ医学誌であるランセットは武見を「カリスマ(catalytic charisma)」と評し特集している。保健政策に関わる国際的なこれらの活動は、日本の外交力を強化するものとして評価されている。また、少子高齢化については「2030年以降の生産年齢人口の急減」に強い危機感を示し、女性の社会進出や高齢者雇用、外国人労働者受け入れ、医療・介護分野のデジタル化などの政策を訴えている。
人間の安全保障に関する活動
武見は、1990年代後半から日本外交における「人間の安全保障」の推進に深く関与してきた。冷戦後、国際社会における「人間の安全保障(Human Security)」概念の重要性が高まるなか、外務省や内閣の議論を通じて同概念を政策として体系化する役割を担った。特に、アジア金融危機後の社会的弱者への支援強化や、ODAの改革議論において「人間中心の安全保障」の必要性を政府内で主張し、国連への「人間の安全保障基金」創設(1999年)や「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の制度設計にも関与した。2000年の国連ミレニアム・サミットでは、日本政府が主導して「人間の安全保障委員会(Commission on Human Security)」の設立を提案。この委員会では、緒方貞子(当時JICA理事長)やアマルティア・センらと共に議論を進め、保護(Protection)と能力強化(Empowerment)を柱とする政策枠組みの形成に寄与した。また、北海道洞爺湖サミットに向けては、G8諸国に対し、ヘルス・システム強化(HSS)の必要性を人間の安全保障の観点から提唱するなど、グローバル・ヘルス分野における人間の安全保障の実践的活用にも取り組んだ。この枠組みは、後年のJICAによるODA実施方針や日本の多国間外交の基礎にもなっている。武見はその後も国際的なシンポジウムや政府内議論において「人間の安全保障」を国際社会の共通課題として位置づけ、特に「欠乏からの自由」と「恐怖からの自由」を組み合わせた新たな安全保障モデルの確立に注力してきた。
海洋基本法に関する活動
東シナ海における中国の調査船問題などの海洋安全保障上の問題、排他的経済水域・大陸棚などの海域をめぐる政策課題に対応するため、2006年4月、超党派の政治家と有識者からなる海洋基本法研究会(代表世話人:武見敬三)を設立。2007年の海洋基本法成立に尽力した。
その後も「EEZ(排他的経済水域)を守るための国家の意志を強化する必要があり、覚悟を決めた対応が必要となる。大局的な視点を持った政治家的アプローチが今求められている」と述べて個別的利害対立を超えた総合的対応の必要性を訴え、2013年の新・海洋基本計画制定に尽力するとともに自民党海洋戦略小委員会の委員長として継続的な政策の実現をリードした。海底鉱物資源開発、海洋の安全保障、排他的経済水域の開発・利用・保全、海洋産業の育成などが重要な課題であるとしている。
自殺対策基本法に関する活動
2006年、自殺者数が多い日本の深刻な状況に対処するため、「自殺対策を考える議員有志の会」で中心的役割を果たし、議員立法の立役者として党派を超え自殺対策基本法の成立に尽力した。
日本の自殺者数は1997年から98年にかけ急増し毎年3万人を上回る状況が続いていたが、政府内の担当部署も曖昧で、自治体を含め政府の戦略もない状況だった。この状況を受け武見ら厚労委のメンバーを中心に超党派の参院議員の動きが活発化、有志議員と民間が連携した立法活動が実り自殺対策基本法が成立した。同法は社会的な取り組みとして自殺対策を国や地方公共団体の責任と規定しており、内閣府への「自殺総合対策会議」の設置や民間団体との連携なども盛り込み、国を挙げて総合的な自殺対策に取り組む契機となった。その後も継続的に自殺対策に尽力、2019年には「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案」が成立した。
人道外交に関する活動
超党派の「人道外交議員連盟」会長として、日本政府の人道支援政策強化に積極的に関与している。特にパレスチナ・ガザ地区における人道危機への対応として、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への継続支援を提言し、医療分野での具体的貢献としてメディカルエバキュエーション(医療目的の避難支援)への参画を提言しているほか、二国家解決を支持し、その推進を図っている。
世界保健機関(WHO)のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)親善大使としての活動
2019年、長年にわたるグローバルヘルス分野での貢献、なかでも「誰一人残さない持続可能な保健医療制度の確立を目指す」UHCの推進を世界的に主導したことが国際的に高く評価され、マイケル・ブルームバーグらとならび、世界で10人の世界保健機関親善大使に任命された。
WHOテドロス事務局長は委嘱の辞において、これまでのグローバルヘルスにおける功績を称えるとともに、「UHC達成に向けて日本のリーダーシップは重要であり、日本の政治家および学者の立場からも発信できる武見議員の今後の親善大使としての活躍に大いに期待する」と述べた。
同年9月23日に開催された第74回国連総会のUHCハイレベル会合では、武見はパネルディスカッションに登壇し、各国が独自のロードマップを策定し、UHCの推進に取り組むべきであると提言した。また、UHC政治宣言の採択を踏まえ、持続可能な保健財政の強化、プライマリーヘルスケア(PHC)の推進、非感染性疾患(NCD)や感染症対策、医薬品アクセスの改善、保健人材の育成など、多岐にわたるUHCの重要課題への取り組みを強調した。武見は、UHCを単なる医療制度改革にとどめず、社会経済の発展と結びつけた総合的な枠組みとして推進する必要性を訴え、日本の経験を生かした国際協力の重要性を強調した。
グローバル・ヘルスに関する活動
2007年11月より、アメリカ合衆国ハーバード大学公衆大学院及び日米関係プログラムの客員研究員として渡米し、ハーバード大学を拠点としてエイズ等感染症、母子保健、乳児死亡率の改善等、国際社会の喫緊の課題を内容とする「グローバルヘルス(Global Health)」を研究テーマに各国で論文発表、国際会議に関わっている。2008年の、G8北海道洞爺湖サミット・フォローアップ「保健システム強化に向けたグローバル・アクションに関する国際会議」の後、国際タスクフォースの主査として「保健システム強化に向けたグローバル・アクション G8への提言」を発表した。2011年には、世界的医学雑誌ランセットの日本特集号国内実行委員会委員長として、『ランセット』日本特集号「国民皆保険達成から50年」を発表した。
2016年より、外交専門誌『外交』に「開発と安全保障をつなぐ日本のグローバルヘルス戦略」(2016年)、「国際保健外交の現状と日本の役割」(2017年)等を発表。グローバル・ヘルスワーキンググループの委員長も務めた。また、UHC2030運営委員会の共同議長らとともに、2023年にはCOVID-19パンデミックの教訓を踏まえたグローバルヘルス体制の抜本的強化を訴え、気候変動や人道危機といった新たな健康脅威に対する備えとして、医療システムのデジタル化、医療DX、政治的リーダーシップ、社会全体の参加、ジェンダー平等の促進、および法規制整備の重要性を提唱している。また、自由民主党国際保健戦略特別委員会委員長として、アジア健康構想(AHWIN)の推進、医薬品・医療機器の規制調和を目的とした医薬品医療機器総合機構(PMDA)のアジア拠点整備の推進を通じて、日本およびアジア地域の医療システム強化に取り組んでいる。また、トランプ政権再登場を見据えた発言として、「日本は、米国の国際機関からの撤退や国際秩序の混乱に備え、ミドルパワーとしてグローバルヘルスなどで国際社会における役割を強化すべき」との見解を示している。
福島健康管理調査に関する活動
2012年3月1日に福島県民健康管理調査で世界の英知を結集する必要があるとともに、世界に向けて情報を発信していく必要があるとして福島県立医科大学に国際連携部門が設立され、山下俊一福島県立医科大学副学長からの客員教授就任の依頼を受けて同年に福島県立医科大学客員教授に就任した。
非正規雇用労働者の待遇改善に関する活動
2025年2月より、超党派「非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活を考える議員連盟」の会長として、非正規労働者の待遇改善を目的とした活動を推進している。同議連では、非正規雇用から生じる格差の是正、希望の持てる生活の実現を目指し、議員立法によるワークルール教育の法整備や待遇改善政策の提言などに取り組んでいる。
緊急避妊薬に関する活動
自民党の「地域で安心して分娩できる医療施設の存続を目指す議員連盟」の会長であり、この議連は日本産婦人科医会の働きかけで発足した。2022年12月26日、「緊急避妊薬の安全使用や悪用防止を図る」ため、議員連盟会長としてOTC化(市販化)に慎重な対応を厚労相に要請した。このため、緊急避妊薬の市販化を目出す女性団体からは、4万件以上の意見の多数が市販化賛成というパブリックコメントを経てもなお試験運用開始も始まらない同薬について、厚生労働相としての中立性について注目されている。緊急避妊薬は、WHOの必須医薬品であり、約90カ国で処方箋なしで薬局で購入できるが、日本では医師の処方箋が必要である。
医療DXに関する活動
自由民主党政務調査会の「社会保障制度調査会・デジタル社会推進本部 健康・医療情報システム推進合同PT」において、医療DX推進を主導している。2022年5月には『医療DX令和ビジョン2030』を提言し、「全国医療情報プラットフォーム」の創設、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定業務のデジタル化(診療報酬改定DX)の推進を提案した。さらに、2023年4月には「医療DX令和ビジョン2030」の具体的実現に向けた提言を取りまとめ、厚生労働省の司令塔機能強化、医療情報の二次利用(研究・開発活用)の促進、個人健康情報(PHR)の推進を通じて、国民が最適な医療を受けられる社会の実現を目指している。また、デジタルヘルスの重要性を認識した経験を踏まえ、日本国内における医療DXの推進に尽力するとともに、世界の保健システムにおいてもデジタル技術が医療サービスの質や効率性、健康の公平性向上に重要であることを強調していると学術誌にも寄稿している。
看護師・保健師に関する活動
日本の地域保健における看護師・保健師の役割を高く評価し、地域における保健指導・疾病予防・在宅訪問・データを用いた地域ニーズの把握などを通じて、超高齢社会における地域ケアや健康寿命の延伸に貢献してきたと指摘するとともに、WHOや世界銀行と協力して設立を進める「UHCナレッジハブ」においても地域包括ケアや看護職の役割を重視している。
少子化・人口問題に関する取り組み
少子化問題について「日本の少子化はフランスなど欧州諸国よりも急速に進行しており、社会的なあつれきや経済停滞、安全保障リスクを引き起こす」と指摘している。介護保険導入(2000年)当時に少子化対策も同時に進めるべきだったと述べ、非正規雇用の増加やデジタル化の遅れが少子化の一因になったとの見解を示した。岸田内閣による児童手当の所得制限撤廃には賛成の立場を取り、「女性の社会進出と職場復帰が前提となる社会構築」を訴えている。また、少子化が安全保障に与える影響についても警鐘を鳴らし、「人口減は軍事力の基盤を脅かし、欧米諸国では女性兵士や無人機などの導入が進んでいる」と発言している。
中国・台湾政策に関する活動
長年にわたり中国および台湾との外交関係の歴史や現状に詳しく、自民党内で台湾と中国両方の議員連盟に所属する立場から発言を続けている。台湾問題については「台湾の戦略的重要性は半世紀を経ても変わっておらず、台湾の民主主義体制を守るべき」と述べ、台湾有事リスクに備えた日本の防衛力強化と、日中間の戦略的互恵関係の両立が重要との考えを示している。自民党内で「教条的に中国との対立を志向する勢力」と「対中協調を重視する現実主義的立場」の二極化が進む中、自信を後者に位置づけ、自らは「対話と抑止の双方を重視するバランス外交」の必要性を訴えている。
人物
旧統一教会との関係
ジャーナリストの鈴木エイトによると、旧統一教会関連団体との関係について、2019年7月の参議院選挙期間中の個人演説会に、勝共UNITEの主要メンバーや、都内教区で政治家などの渉外を担当していた幹部信者など、複数の統一教会関係者が参加していた。また演説会には、菅義偉官房長官や菅原一秀衆院議員も応援で登壇した。2013年の参議院選挙では、教団内部文書に東京選挙区の推薦候補として武見の記載があった。
親族
父は日本医師会の会長を務めた武見太郎。麻生グループ代表麻生泰(麻生太郎衆議院議員の弟)の妻である和子は姉であり、武見自身麻生太郎とは母方のはとこにあたる。外祖父は秋月種英で、大久保利通、牧野伸顕らの子孫にあたる。 家族は妻と娘と2人の息子。
- 家系図
経歴
- 1951年 元世界医師会会長・日本医師会会長の武見太郎の三男として生まれる。
- 1958年 松濤幼稚園を経て慶應義塾幼稚舎に入学。
- 幼稚舎5年生よりラグビー部に所属
- 東京都6中学リーグ戦優勝
- 全国高校ラグビー大会第三位(夢の花園ラグビー場)
- 全国学生ラグビー選手権大会第三位(レギュラー選手)
- 1974年 慶應義塾大学 法学部政治学科 卒業
- 1976年 慶應義塾大学大学院 法学研究科政治学専攻 修士課程修了
- 1976年 台湾師範大学国語中心に留学。
- 1977年 ハーバード大学 フェアーバンクス記念東アジア研究所 客員研究員
- 1980年 慶應義塾大学大学院 法学研究科政治学専攻 博士課程満期退学
1980年 東海大学 政治経済学部政治学科 助手 - 1983年 東海大学 政治経済学部政治学科 専任講師
- 1984年 テレビ番組「CNNデイ・ウォッチ」で約3年間アンカーマンを務める。
- 1987年 テレビ朝日の「モーニングショー」のメインキャスターとして、総合司会を務める。
- 1987年 東海大学 政治経済学部政治学科 助教授
- 1992年 ハーバード大学 フェアーバンクス記念東アジア研究所 客員研究員
- 1995年 東海大学 教授
1995年 日本医師連盟の推薦のもと参議院議員初当選(第17回参議院議員通常選挙) - 1996年 東海大学 平和戦略国際研究所 次長
- 2001年 参議院議員再選(2期、第19回参議院議員通常選挙、議員期間中は外務政務次官を初めに厚生労働副大臣まで複数の役職を担う)
- 2006年 国連事務総長下ハイレベル委員会委員に就任。
- 2007年 参議院議員を落選(第21回参議院議員通常選挙)
2007年 日本医師会総合政策研究機構 特別研究員
2007年 ハーバード大学公衆衛生大学院及び日米関係プログラム 客員研究員に就任。渡米。 - 2008年 日本国際交流センター シニアフェロー(Senior Fellow, Japan Center for Int’l Exchange)
2008年 長崎大学医学部 客員教授 - 2009年 世界保健機関(WHO)研究開発資金専門家委員会委員に就任。
- 2012年 国連母子保健ハイレベル委員会委員に就任。
2012年 身延山大学 客員教授、福島医科大学 客員教授
2012年 参議院議員繰上げ当選(3期、第21回参議院議員通常選挙) - 2013年 参議院議員再選(4期、第23回参議院議員通常選挙)
- 2014年 慶應大学医学部客員教授
- 2017年 参議院自民党政策審議会長
- 2019年 参議院議員再選(5期、第25回参議院議員通常選挙)
2019年 WHO ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 親善大使 - 2020年 参議院自民党議員副会長
- 2021年 国連開発計画(UNDP)「人間の安全保障に関する特別報告書ハイレベル諮問パネル」 共同議長
政策・主張
- 選択的夫婦別姓導入への賛否について「賛成」としている。また、別の記事では、選択的夫婦別姓制度の導入については「反対ではない」とし、党内の意見集約の必要性を述べている。
- 日米安保体制はもっと強化すべきとしている。
- 「他国から攻撃が予想される場合は先制攻撃をためらうべきではない」という設問に対し、「どちらかと言えば賛成」と回答。
- 憲法9条を改正して自衛隊の役割や限界を明記すべき。
- 集団的自衛権を行使できるよう憲法解釈を変更するべき。
- 日本の原発について当面は必要だが、将来的に廃止すべき。
- 人口減少・高齢化対策として、医療DXの推進、外国人労働者の受け入れ促進、医療インバウンド拡大による医療財源確保を主張。また、別の記事では、生産年齢人口の急減対策として、外国人労働者の受け入れ拡大に前向きな立場を示し、法整備の継続に言及している。
- 少子化対策として児童手当の所得制限撤廃に賛成し、「支援強化」を主張している。また、少子化が軍事力や国家の安全保障に及ぼす深刻な影響を指摘し、女性活躍や労働力多様化の必要性を訴えている。そして、非正規雇用の増加やデジタル化の遅れが、少子化を加速させたと分析している。
- 国民皆保険制度の維持と、医療インバウンドの推進を成長戦略の一環と位置付けている。また、別の記事では、医療DXの推進について「マイナ保険証」や電子カルテの全国共有化を積極的に支持し、救急医療の質向上や医療現場の効率化に資するものと述べている。
- 平和主義を「戦略的意志」とし、人道外交を強化しながら、安全保障上の「戦略的能力」の強化も求めている。また、別の記事では、日本の役割について「国際社会でミドルパワーとして、特にグローバルヘルス分野で米国の縮小分を補うべき」とし、国際機関との連携強化を主張している。
- ガザ地区の人道支援拡充を提唱し、メディカルエバキュエーションを含む保健医療支援の実施を推進。
- 中国との関係においては、力による現状変更を牽制しつつ、共通課題への連携を重視している。また、中国の経済不安や国内問題が、日本への対抗措置や台湾有事リスクの高まりに繋がるとの懸念を表明している。そして、台湾海峡の緊張について「中国の軍事的優位が進めば危機が高まる」と述べ、日米同盟や国際秩序の安定が重要との立場を示す。日中関係について「不必要な対立は避けつつも、中国の行動に警戒を怠らない」との立場を示す。
選挙歴
主な所属議員連盟
- 東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止法を実現する議員連盟(副会長)
- 日本の領土を守るため行動する議員連盟
- 海事振興連盟
- 日華議員懇談会
- 選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議連
- 世界銀行国会議員連盟
- 賃貸住宅対策議員連盟
- 国民歯科問題議員連盟
- ポリオ根絶議員連盟
- 自由民主党タクシーハイヤー議員連盟
- 日本に誇れる漢方を推進する議員連盟
- 栄養士議員連盟
- 地域で安心して分娩できる医療施設の存続を目指す議員連盟(会長)
論文
- 武見敬三. ロバート・R・シモンズ著 林建彦・小林敬爾訳「朝鮮戦争と中ソ関係」. アジアクォータリー. 1976-04 1976;8(2):130-132.
- 武見敬三. 米国統合参謀本部の台湾政策 : 「平時」と「戦時」の相克. 行動科学研究. 1981 1981;15(1):63-76.
- 武見敬三. 地域医療にも国際保健という視点を. 日本病院会雑誌 = Journal of Japan Hospital Association.2003-08-01 2003;50(8):1186.
- Takemi K, Jimba M, Ishii S, Katsuma Y, Nakamura Y. Human security approach for global health. Lancet.Jul 5 2008;372(9632):13-14.
- Reich MR, Takemi K, Roberts MJ, Hsiao WC. Global action on health systems: a proposal for the ToyakoG8 summit. Lancet. Mar 8 2008;371(9615):865-869.
- Reich MR, Takemi K, Roberts MJ. 保健システム強化のためのグローバルアクション--洞爺湖G8サミットへの提言. 日本医師会雑誌. 2008-07 2008;137(4):719-728.
- Reich MR, Takemi K. G8 and strengthening of health systems: follow-up to the Toyako summit. Lancet. Feb7 2009;373(9662):508-515.
- Kawahara N, Akaza H, Roh JK, et al. The eighth Asia cancer forum: seeking to advance the outcomes of theUN summit: 'global health as the key to a new paradigm in cancer research'. Japanese journal of clinicaloncology. Dec 2012;42(12):1222-1231.
- 武見敬三. (2016). 開発と安全保障をつなぐ日本のグローバルヘルス戦略 (特集 G7 伊勢志摩サミットを展望する). 外交= Diplomacy, 36, 70-77.
- 武見敬三. (2017). 国際保健外交の現状と日本の役割. 外交= Diplomacy, 43, 95-101.
- Takemi K. Preface to the Special Issue by Keizo Takemi, Minister of Health, Labor and Welfare, Japan. Health Systems & Reform. 2024 Dec 17;10(2):2390851. doi:10.1080/23288604.2024.2390851. Epub 2024 Oct 22. PMID: 39437243.
- Takemi K, Inoue H, Rodriguez DC, Tuipulotu A, Rasanathan K. Public health nurses in Japan. Lancet. 2024 Aug 10;404(10452):521-522. doi:10.1016/S0140-6736(24)01483-1. PMID: 39127470.
- Espinosa MF, Andriukaitis VP, Kickbusch I, Nishtar S, Saiz E, Takemi K, Barron GC, Koonin J, Watabe A; UHC2030. Realising the right to health for all people—UHC is the umbrella to deliver health for all. Lancet Global Health. 2023 Aug;11(8):e1160-e1161. doi:10.1016/S2214-109X(23)00202-4. PMID: 37146627; PMCID: PMC10154000.
- Takemi K. Lecture No. 6 Asia Health and Wellbeing Initiative (AHWIN) and cancer. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2021 May 18;51(12 Suppl 2):i24-i27. doi:10.1093/jjco/hyaa263. PMID: 34002790.
- Davies SC, Akksilp S, Takemi K, Matsoso P, Da Silva JB Junior. The future leadership of WHO. Lancet. 2016 Jan 23;387(10016):321-323. doi:10.1016/S0140-6736(16)00105-7. PMID: 26842435.
- Takemi K. Proposal for a T-Shaped Approach to Health System Strengthening. Health Systems & Reform. 2016 Jan 2;2(1):8-10. doi:10.1080/23288604.2015.1123339. PMID: 31514654.
- Gorna R, Klingen N, Senga K, Soucat A, Takemi K. Women's, children's, and adolescents' health needs universal health coverage. Lancet. 2015 Dec 12;386(10011):2371-2372. doi:10.1016/S0140-6736(15)01176-9. PMID: 26700516.
- Reich MR, Harris J, Ikegami N, Maeda A, Cashin C, Araujo EC, Takemi K, Evans TG. Moving towards universal health coverage: lessons from 11 country studies. Lancet. 2016 Feb 20;387(10020):811-816. doi:10.1016/S0140-6736(15)60002-2. Epub 2015 Aug 21. Erratum in: Lancet. 2016 Feb 20;387(10020):750. PMID: 26299185.
- Heymann DL, Chen L, Takemi K, Fidler DP, Tappero JW, Thomas MJ, Kenyon TA, Frieden TR, Yach D, Nishtar S, Kalache A, Olliaro PL, Horby P, Torreele E, Gostin LO, Ndomondo-Sigonda M, Carpenter D, Rushton S, Lillywhite L, Devkota B, Koser K, Yates R, Dhillon RS, Rannan-Eliya RP. Global health security: the wider lessons from the west African Ebola virus disease epidemic. Lancet. 2015 May 9;385(9980):1884-1901. doi:10.1016/S0140-6736(15)60858-3. PMID: 25987157; PMCID: PMC5856330.
- Takemi K. Cross-boundary cancer studies at the University of Tokyo: Changes in Japan's global health policies: current stage in approaches to strengthen health systems. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2014 Feb;44 Suppl 1:i65-68. doi:10.1093/jjco/hyt209. PMID: 24516217.
- Takemi K. 高齢化先進国日本の役割. 日本気管食道科学会会報. 2013;64(2):57. doi:10.2468/jbes.64.57.
- Takemi K, Kumazawa J. 未来志向の医療制度改革. 日本化学療法学会雑誌. 2002;50(9):606-610. doi:10.11250/chemotherapy1995.50.606.
出演番組
レギュラー番組
イレギュラー番組
- ビートたけしのTVタックル
- 太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。
脚注
注釈
出典
関連項目
- 日本医師連盟推薦の国会議員
- 宮崎秀樹 - 医師、元・参議院議員。第14回参議院議員通常選挙(1986年)で初当選し、以後3期務めた
- 西島英利 - 医師、元・参議院議員。第20回参議院議員通常選挙(2004年)で初当選し、以後1期務めた
- 慶應義塾大学の人物一覧
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- 武見敬三 (keizo.takemi.fan) - Facebook
- たけみ 敬三(自民党 参議院議員・東京) (@TakemiKeizo) - X(旧Twitter)
- 武見敬三 - YouTubeチャンネル